ひとひら通信2000/7月
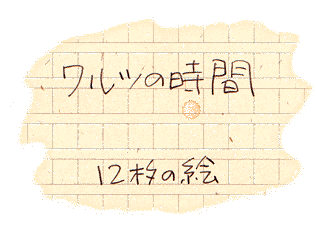
|
たおやかな沈黙 |
|
スペインのマヨルカ島に船でついた時には、私の頭の中の夢遊病は、私の体の中の海底に音もなく着地していた。 何日か2流のリゾートホテルにフぬけの観光客として滞在したら、夢遊病はゆっくりとさめはじめ、自分が何でこんなところに、それも、二人のニューヨークの女にはさまれて、海岸に寝そべっているのかを、とても異様に感じられてきた。 ちょっと前にストックホルムで、私の23歳の誕生日を祝ってくれた。サラとマーシーは、そんな私の気持ちをわかってかわからないでか、とても陽気に、ホテルのボーイをからかってはしゃいでいた。 「イナカニ行けば、農家の2階をやすくで、かしてくれるらしいの、1ヶ月くらいのんびりしてみようよ」 ニューヨークで男と別れて、日本にやってきて、私のところへころがりこんで来たサラ。押し出される感じで家を出た私の妻。そのスキマを埋めるように、サラから呼ばれて、ニューヨークからやって来たマーシー。彼女も男と別れたところ。3人で小さな部屋できめた大脱出。日本からスウェーデンのストックホルムで見つけた。マヨルカ島行きの、これまたやすいホテル付航空券。2ヶ月近い奇妙な3人旅が辿り着いたのは、マヨルカから車で1時間、カン アルボ−ナと呼ばれる小さな小さな村だった。 赤土の大地と果てしなくつづくオリーブ畑。2階の大きなテラスから見えるのは、それだけだった。夕日が沈むとまわりは闇。ポツンポツンと灯る家のあかりが、その闇の深さをさらに濃くしていた。 安いワインが、3人の頭の中の夢遊病を再び発病させ、カンアルボーナでの仮の暮らしは、この世、あの世とゆっくり揺れつづけた。ホテルのボーイがウサギの肉とハッシッシを土産に遊びに来た。サラはフリーセックスを暮らしに持ち込み、マーシーは文学少女の世界を広げはじめ、私は歌をつくろうと少しあがいたけれど、赤土とオリーブとワインにやられて、ただただ時の流れの中にかくれていた。 |
|
夜の闇 |
|
暖炉の火を見つめ、テラスから満点の星空を眺め、そのまま眠ってしまおうと思った。なんだか心の奥の深い闇に飲こまれてゆく感じがした。サラとマーシーが何か言い争っている声がして、また静けさが深まった。 ずっと遠くから、ガランコローンと音が聴こえたような気がした。風向きが変わり、そのガラーンコローンが揺れ動き、すこしずつこっちに近づいて来た。起き上がってテラスから闇へと眼をこらすと、ガランコローンは少し遠のいた。オリーブ畑の小道に灰色のかたまりが見えた。ガランコローンとそのかたまりが近づいて来た。 それは羊たちの小さな群れだった。首につけられた鈴は、にぶい音でガランコローンと鳴りながら、すぐそこの小道を遠去かろうとしていた。羊たちのいちばん後ろをヨロヨロと歩いているじいさんが、私の方を見上げた気配がした。 羊たちもガランコローンも、ゆっくりとフェイドアウト。もとの闇がそのあとを包みこむように広がっていった。 |
|
ワルツの時間 |
|
中学校の運動会でのフォークダンス。マイムマイムマイム。コロブチカ。どこかで強く魅かれ手いる女の子まで、あとふたり。クルッとまわってトントントン。この子と別れて次の子へ、その子も悪くないけど、やっぱりあの子。なのに、妙にあっけないエンディングで曲は終わってしまう。ザワッとフォークダンスの輪は崩れて全部終わり。 高校の友だちから売りつけられた、訳のわからないパ−券。ベンチャーズ全盛のテケテケテケのエレキギター。ゆったりとした8ビートの、いかにもアメリカンのバラード。みんなが、あいつは男好きだという女の子とのチークダンス。首にまわされる彼女のウデ。妙にズシッとしている腰まわり、ひけていた腰が少し大胆に揺れる。鼻にからみつく彼女の髪。隣を気にするのをやっとやめた時に、1曲終わり。下手クソなドラムのイントロでまたまたモンキーダンス。なんだかホッとして手も足もバラバラにして、イエイなんて言ってみるあの青さ。 もう完全にセットアップされている彼女の部屋。和紙を使った照明機具。テーブルの上にローソク。天井にインドの布かなんか垂れ下がり、香までたいてあったりする。ワインとハッパ。ポータブル蓄音器。ガシャッとレコードの入れ換わる音。踊りましょう。というキザなセリフ。触れあいましょうという意味に自然に聞けた自分。そのまま朝まで踊りつづけたいという女。踊るという身体の感覚。唄うということと違う感覚。 身体の震え。身体の硬直。身体のゆるみ。身体のたゆたい。身体のおそれ。身体の目ざめ。身体のおとろえ。身体の揺れ。身体の静止。そして身体の消滅。 たてから横へ、直線から曲線へ、平面から立体へ、細やかさも激しさも包み込んで、いつか大きなワルツを踊ってみたい。ひとりでみんなと、みんなとひとりで、ひとりとひとりで、みんなとみんなで。 |
|
緑の匂い |
|
恋の彼方へ 裏庭のむこう側は果てしなくつづく菜の花畑で、畑の真ん中の古い井戸からは冷たい水があふれ出した。叔父の遺体の前に座った。 しばらく叔父の顔を見ていた。それはもうそれだけで景色であり、その景色の地下水脈が音もなくうねっているようだった。今までの旅の景色がゆっくりと浮かびあがって来る。 そこにいる人間の姿が景色の中にとけこんでゆく。大平洋がニューヨークの摩天楼がサハラ砂漠が、ナイル河でさえそこにたどり着くのがわかった。 種子島の港に北海道の雪が、青い海に浮かぶ島々が宇宙の外へ外へと、ものすごいスピードで離れてゆき、歌が曲がりくねり突然伸びやかに流れて行った。 叔父の顔が船になり、やっと背後にいる人たちの気配へと私は帰って来た。 家の外へ出た。極楽寺にもうくることはないかもしれないと思っていた。何をだかわからないけど、しっかり眺めておこうと思った。 曲がって少しづつ登る道のリズムは変わっていなかった。畑仕事の途中おばさんが、私の顔をやわらかく見つめてから、「息子さんか」と言った。小型トラックの中から声をかけていた男も「息子さんかのぉ」と言った。 極楽寺の空気が妙に柔らかくなって来た。 「いえ、甥になります」 そんなことはどうでいいことだった。 なんだか漠然と、命の問題なんだと感じた。 「焼きあがりました」 男はそう言って、私たちを案内してくれた。 適度に拾う骨を残しつつ焼くのは技術がいるのだそうだ。 灰をうっすらかぶった人間の燃え残った身体はあまりに小さい。左胸だったあたりの少し下に、湖のそこみたいな緑がにじんでいる。 「あのあたりが悪かったんだろうね。色が出てるもんねぇ」 母親がボソッと言った。 焼き場を出てバスに乗り込んだら、雨が激しくなった。 バスの中にはいわゆる親類縁者がひとにぎり。 叔父の娘が膝の上の骨壷をひとなでして言った。 「あったかいよまだ。死んでからやっとあったかくなったってねぇ」 叔父は決していい父親ではなかったらしい。 少し沈黙はあったけど、ムードは決して悪くなかった。 「なんだか遠足みたいだね」 私は小さな声でそう言ってみた。 焼けた骨の左胸あたり。 湖の底みたいな緑色。 それが私の中に景色となって残った。 |
|
あの時はどうも |
|
「女に走るってどういう意味」 そう聞かれて、答えにつまった。 「そうだなあ」 何人か女の顔が浮かんだ。 最初の女は15歳だった。 私は19歳で、とりあえず家を出てみたけれど、何をどうしていいのかわかってはいなかった。彼女は、すでにひとりで暮らしていた。銀座でホステスをしているという話だった。ずいぶん年上に見えたけれど、ほんとのトシを聞いて、まさかと思った。いっしょに暮らしはじめた。というより、彼女の暮らしの中へ転がり込んだだけだったのかもしれない。全くガキだった私に気づいて、彼女は何度も別れようとした。そのたび私は追いかけた。ひとりで生きていけない自分をつっぱりながらもさらけ出した。 小さなドラマがいくつかあって、飽きて疲れて落ち着いた。6畳ひとまの暮らしがはじまって、今度は社会的なドラマへと向かいはじめた。 東京キッドブラザーズのニューヨーク公演。オフ ブロードウェイの劇場、シェリダンスクエア、プレイハウスでの「ゴールデンバット」は1年近いロングランとなった。 女に少し夢中になって、それがドラッグでばらけ、日本に舞い戻って来た時、ガキはガキなりに自信みたいなものが生まれていた。 俺には俺の音楽がある。ニューヨークで認められた才能がある。 17歳になっていた彼女が、ふたりで暮らしていた部屋を出て行った時。なにも考えずに、ニューヨークから来た女としばらく、その部屋で過ごした。 その女から、1年後、ニューヨークで、私は見事に捨てられた。 |
|
つなわたり |
|
小学生の時、サーカスを見た。 ピエロの哀しさは、まだわからなかった。 オートバイが大きなカゴの球の中を、爆音とともに、グルグルグルグル、たて横ナナメに走り回っているのに目を奪われた。最後になんだかとっても哀しくなった。 空中ブランコからは何も感じなかった。宙を飛ぶ女も、さかさまにブランコから両手をダラリと下げた、受け手の男も、そこに哀しさはなかった。落ちたらどうなるのかというスリルも、下に張ってあるネットを見てからなくなった。 問題は、つなわたりだった。 そいつは、とってもひとりぽっちだった。 男の持つ長い棒がゆらゆらと動き、ピーンと張られたロープとクロスしていた。つま先がロープに踏み出される時の緊張感が伝わってきた。オートバイの騒音も、空中ブランコの華やかさもそこにはなかった。 一直線の静けさだけがあった。 真ん中あたりまで渡って来て、男は小さく息をついたようだった。ロープがタテにゆっくり揺れはじめ、バランスをとっている棒を、男は上下に大きく動かした。身体がグラッと傾き、片足が少し宙に浮いた時、客席の沈黙が、沈黙のままどよめいた。 そのどよめきが、男の耳に届いたらしく、手にもった棒を少し振った。 ひとりで空中を歩いている男が、そのひとりぽっちを楽しんでいる。 小学生だった私が、正確にそう感じたわけではなかったが、なんだか、その男を見上げながら、しみじみとした想いになった。 ゆっくりと渡り切った男が手を上げ、いい拍手がザワザワと起こり、ロープを伝って地上に降りた男は、あっさりと退場した。 ひとりぽっちはやっぱりきれい。 また登場してきたピエロが、今度はとても哀しく見えてきた。 |
|
流れ星物語 |
|
夜の闇の中に身を置く。 都会の中では、ほとんど不可能になった。 夜の中に、ポツンとひとり。 そうなることに、人間はおそれを抱いているのかもしれない。 闇を排除する街の灯り。沈黙へ辿り使えない騒音の壁。 闇から見上げる夜空のむこうの宇宙。 沈黙から生まれ落ちる一滴の言葉。 そこに向かう為には勇気がいる。 自分の中の宇宙と向きあうというのは、自分の中の見知らぬものに向きあうということ。 沈黙の中にひそむということは、自分の中の不思議に、ただたたずむということ。 今風に言えば、それをネクラ、オタクと片ずけてしまう行為になる。 無限なるもの、はてしなきもの、そこへ向かうことを、なぜやめてしまうのだろう。 そこへ向かうものの足をなぜひっぱるのだろう。 「おまえもやっとオトナになったな」 「やっとわかってきたみたいだな」 オトナとは社会の部品になると言うこと。 わかってきた、とは、わからないことのおもしろさへの興味も、その感受性も閉ざしてしまうこと。 夜の闇から生まれる光。ちんもくの中から生まれる言葉。 それはそこへたどり着くための旅が生きているということ。 サハラ砂漠の地平線から昇る太陽 種子島の海に沈む夕陽 ハワイ島の水平線からくる満月 そして 闇から見上げる星座を、横切って消える、流れ星 そのあとに残された沈黙の宇宙 |
|
降りつもるもの |
|
たしかオシャマンベだったと思う。 札幌から友人の車で、アイスバーンになった国道から県道に入ったら、車はボブスレーみたいに滑りながら坂道を下った。外は吹雪に近い雪で、こんな夜のライヴに客が来るとはとても思えなかった。 小さな喫茶店に10人以上の客が集まったことに、なんだかほとんど感動した。 すとーぶにくべられたマキがいいタイミングでパチンとはね、その音をバックに、妙に透き通った感じで唄えたことだけは、よくおぼえている。 そろそろ最後にしようかなと思った頃、ドアが開き、外から白い雪が彼女といっしょに入ってきた。 「もう、最後の1曲かもしれないけど」 そう言った時、ちょっとうなずいた彼女の身体にかくれるようにして、小さな女の子が私に向かって手をふった。 彼女達がストーブの横に座ってから、4曲ほど唄って、ライヴは終わった。 何人かが雪の中へと小走りに去り、何人かにサインをして、喫茶店のマスターが冷たいビールをもってきてくれた。 「外は吹雪、中はストーブで熱い時に飲む冷たいビールがうまいんだわ」 気のいい北海道の男がそう言う。 そのストーブの側に座っていた女の子が、私を手招きしている。 一口、ビールを飲んでから近よる。 女の子は、私の顔を見つめながら、隣の女、多分母親のヒザをパタパタ叩いている。 女が照れくさそうに言う。 「やめなさいよ、ごめんなさいね、この子が気をきかせるつもりなの」 もう一口、ビールを飲んでから、彼女の隣に座る。 「おぼえてないでしょうね」 彼女は、どこか水商売の気配を漂わせていて、若いのか老けてるのか、わからない顔をしていた。 もう一口ビールを飲んだ。 「新宿のルイードでいっしょに飲んだことがあるんですけど、もう10年ぐらいまえだもんね」 ルイードはライブハウス。私が20代の頃、月に1回ぐらいのペースで唄っていた。 毎年1枚ずつアルバムを出し、そこそこに客が入っていた、いわゆるシンガーソングライター時代の話だ。 「あれから、何かいろいろあったしね。」 「そうよね」 しばらく彼女とはなしているあいだ、女の子はうれしそうに彼女と私のヒザに手を置いたりしていた。 「何か、おもいだしてきたような気がする」 そう言った私を、彼女は妙に大人の女の目つきで見た。 「うまいわねえ、あいかわらず」 おもいだしたわけではなかった。なにかしみじみした夜だったから、そう言ったのかもしれない。 「ホテルまで行かないと、ほんとに車が動けなくなるよ」 友人が急ぐように言う。 彼女と娘は喫茶店の淡い灯の下に立って、私たちを見送ってくれた。 「わけありの女」 友人が聞いたふうなことをぬかす。 車の窓をあけたら、雪が吹きこんできた。 そのむこうの彼女と娘に手をふった。 彼女達が遠去かり、娘が何か叫んだけれども聞きとれなかった。 「こんな映画あったよな」 そう言った私の言葉は、友人には届かず、車の窓を閉めたら、ヘッドライトがつくるスクリーンに、雪だけが飛びこんできた。 |

|
かすむ景色 |
|
笛吹利明を徳島空港まで送った。有山じゅんじの車で鳴門大橋を渡った。渦潮が、小さな島のまわりにいくつか見えた。 「ひさしぶりに外に出るな」 淡路島の旅館うめ丸に、MBSのAV室でのレコーディングを終えて入ってきて、すでに5日間。昼前に起きて、朝食兼昼食を、旅館の広間で食べ、1階のスタジオに入って、なんだかんだレコーディングしていたら、すでに夜8時前、ひと風呂浴びて、再び大広間で夕食。そのまま毎晩宴会になだれこんでいたのだから、みんな身体は疲れているはずなのに、頭の中のリズムはピーンと張りつめていた。音楽三昧の日々。 「ほんとに楽しかったよ」 今日、東京へ戻る笛吹利明が、空港ビルに向かって、少しよろっと消えていった。 「海まで出てみようか」 四国の鳴門、奥まった入江に浮かぶイカダ。ひとりだけ釣をしている人がいて、防波堤に寝転がって空を見上げた。陽ざしをボワ−ッと全身に浴びたら、グラ−ッと気持ちよく、岸壁にユラユラ揺れるクラゲといっしょに少しだけ眠った。 夕方、うめ丸のスタジオに戻って、しばらくしたら、渡辺香津美が、花博から帰ってきた。彼は昨日、キューバ経由で淡路島に入ってきたので、妙に元気いっぱい、レコーディングがはじまった。 「かすむ景色」。香津美のギターは、花博の花たちをそのまま持ちこんだようなアルペジオだった。有山もゆったりとアルペジオで応え、私も大きなストロークで唄った。声は疲れているけれど、景色のずっとむこうから私をつきぬけて、再び景色に戻って行くようだった。 レコーディングの途中で、ミキシングルームの空気がザワつきはじめ、ニックの顔がチラッと見えた。ハワイからピータームーン一行の到着。 鳴門の渦潮に、キューバの空、そしてハワイの波が加わって、アルバム「ワルツの時間」、レコーディング最後の曲。「かすむ景色」のテイクスリー。そしてピータームーンのギターが間奏に入って、みんなで拍手。その夜は、有山が香津美のウクレレ伴奏で「与作」を絶叫し、ピーターといっしょにやたてきたギタリストのデゥワイトがハワイの古い唄を唄い、宴会は深夜すぎまでつづいた。 |
|
微妙な神様 |
|
わからなかったことが、わかってくる。 そのすっきりとした快感よりも わかっていたことが、わからなくなる。 このめまいにも似た感覚のほうへ、身体が自然に流れてきたようだ。 正体不明の正体が、意味不明の意味がわかってしまうということに、ほとんどおびえていたのかもしれない。 こうあるべきだという正義。みんなそうなんだという常識。すべては愛だという偽善。 そこらあたりで手を打ってしまうことに、ずっと逆らってきた。 逆らうことにとことんあきた時に気づいた。結局は、世の中のやらせ舞台の上で、ちょっと個性派をきどってるだけじゃないのか、と。 わからなかったことがわかってくる。 同じ舞台で演じている自分が見えてくる。 そう感じた時には、もうわからなくなっている。 なぜ? なぜそんな役を演じてきたのか。 なぜ?どうして?この俺が。 そこで、自分自分と向かいはじめると、せっかくわからなくなったことに、違う解答をなすりつけることになってしまう。 そんな時は逃げる。わかろうとしている自分から、わかろうとしている環境から、 それを、旅、と呼んでいたみたいだ。 大きな場面転換。次の物語への準備。もしくは、自分からはじめる、やり直し。 何度、それをくりかえしたろう。 その手口を自分で気づいてしまった今、何をやり直せばいいのだろう。 そうか、そうかもしれない。 自分をわかる、ということをすっかりやめてしまうのはどうだろう。 自分が消えてしまうほど大きな空間を漂ってみればいいじゃないか。 こんな風に、私を越えた何かが、私の目もとでささやきはじめる。 そんな時に、次につくりたいと思っている唄が、はるかかなたから、私を手招きしているようだ。 |
|
海がくる |
|
海に垂直に降りてゆく感じがいい。 5mを越えた時の、水圧のかかり方もいい。 海底の岩に左手をかけ、ゴムの輪を思いっきり引きしぼり、モリの先が魚にまっすぐ向けられた時の一瞬がたまらない。 その時、静けさは全身にしみこんでくる。 時間も空間も静止する。 イントロのギターをジャラーンとブレイクさせる、息を吸い込み一瞬とめる。あの唄い出す瞬間と似ている。 息が限界まできているのに、岩の奥で頭の先をチラチラさせている魚は出てこない。 海底を両足でけって浮上。5mの深さでも海面は頭上はるかに見える。シュノーケルから息を吐き出しながら、ザバンと海面へ出る。思いっきり息を吸い込んで、再び水中眼鏡で海底を眺き込む。魚がひそんでいる岩がユラリと見える。 波が少し高くなってて、遠くなった岩場に白波がくだけ散っているのが見える。 潮が少し引きはじめているらしく、波間に浮かんだ身体が沖にひっぱられているのがわかる。もう1回だけ、それが最後。もう一度海底を眺き込み、大きく息を吸い込むと、シュノーケルの細いクダが笛になって、ヒ−ッと鳴る。 素潜りで魚を追いかけるのをおぼえたのは、種子島のカミヨキノで、さしアミ漁の手伝いをしている時だった。 「オオズキをつくるか」 まだ60前なのに、顔に深いシワを刻み込み、まっクロに陽ヤケしたヤスヨシさんが、そう言った。 海辺の竹林で、なるべくまっすぐな竹を取ってきて、2mほどに切り、タキ火でその油分をとり、銛の先をさしこみ、ハリガネを巻き付けて固定。太い丸ゴムを輪にして、反対側につけて、できあがり。 その日のうちに、3匹の小さなモハミを突いて自慢したら、笑われた。 「いい魚のエサとったなあ」 とれでも毎日潜った。あきずに潜った。 とれる魚は日に日に大きくなったけれど、ほんとにおもしろかったのは、海に潜って行く時の感じだった。 それがいちばんだった。 ヤスヨシさんは60前に亡くなり、それから種子島には行かなくなった。 ヤスヨシさんがつくってくれたオオズキは竹がかわいてバリバリに割れた。 海に垂直に降りてゆく。 その全身で感じる感触。それだけが私の身体に残された。 |
|
たなびく想い |
|
何もないところに、ふと芽生えた小さな小さな「ゆらぎ」から、宇宙は誕生した。 そう言っている人がいます。 その「ゆらぎ」から唄も生まれると思います。 すべては宇宙誕生からはじまった、いのちの流れのひとしずくです。 時空をさかのぼっても、時空をかけあがっても、いのちは、はるかかなたから、はるかかなたへとながれているだけです。 はじまりもおわりも、ここからは見えません。でも感じることはできます。 イントロのギターは、その音が耳に届く、ずっと前から鳴っています。唄い出す、その言葉を乗せたメロディーは、最初の小さなゆらぎを源とした水の流れに浮かびます。エンディングにシャリーンと響き、消えてゆくサウンドは、むこうの景色のそのむこうで、新しいイントロのストリングスへとつながっています。 人間が生まれて死んでゆくのも、たった1曲の唄にすぎないかもしれません。 でも、うたが、いのちの流れに乗って、宇宙に浮かんでいるかぎり、その1曲の唄は、永遠にゆらぎつづける星になるはずです。 あなたも今、1曲の唄を唄っている途中なのです。そのままのあなたで唄いつづけていて下さい。どこかでいつか出会えた時、ふたつの唄の間に、ハーモニーが生まれるかもしれません。 今夜は12枚の絵と題して、下田逸郎のニューアルバム「ワルツの時間」全12曲をお送りしています。 いかがでしたでしょうか それでは最後に、もしくは最初に 「たなびく想い」のゆらぎをお聴き下さい |
最新のひとひら通信ページへ ひとひら通信のバックナンバーページ ■2000年6月:●『ワルツの時間』レコーディングを終えて●下田逸郎ロングインタビュー最終回 ■2000年5月:●『ワルツの時間』レコーディングが始まります●下田逸郎ロングインタビュー2 ■2000年4月:●東由多加に捧げる●『ワルツの時間』レコーディングを直前に控えて ●下田逸郎ロングインタビュー1 ■2000年3月:●レコーディング日誌。●「遺言歌」の紹介記事掲載。 ■2000年2月:●たゆたい ストリングスアンサンブル誕生!。●「遺言歌」の紹介記事情報。 ■2000年1月:●「時間を越えるチャンス」。●XXX情報。 ■1999年12月:●「1999年のラブソング」。●XXX情報。 ■1999年11月:●「弓矢のように」譜面。●XXX情報。 ■1999年10月:●TVCMで「セクシィ」流れてます。●映画「皆月」で「早く抱いて」が主題歌に。 ■1999年夏号:●「下田逸郎物語」本&2枚組CD発売しました ■1998年秋号:●「PARIS 湯玉 HAWAII」&「いきのね」レコーディング日誌 ■1997年春号:●「あ・そ・び・な」全曲紹介&レコーディング日誌 |
|
下田通信所へのお問い合わせは Copyright 1999 下田通信所. All rights reserved. 当ホームページ上で使用されている写真・楽曲等の無断複製、転載、二次使用を禁じます。 |